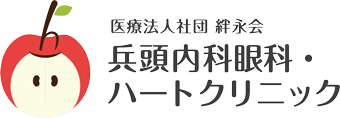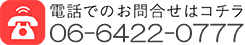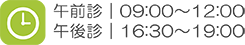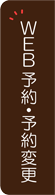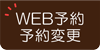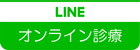2025.07.02 呼吸器の病気
「睡眠時無呼吸症候群」とは何か?日常生活への影響とその改善方法
睡眠時無呼吸症候群とは?定義と特徴
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が10秒以上停止する「無呼吸」状態が1時間に5回以上繰り返される、または7時間の睡眠中に30回以上ある状態を指します。
この症状は、睡眠中に繰り返し呼吸が止まることで体内に酸素が行き渡らず、睡眠の質が著しく低下します。
その結果、睡眠の質が大きく低下し、日中の強い眠気や集中力低下を引き起すなど、日常生活に多大な影響を及ぼすことがあります。
いびきをかく方に多く、中高年の男性に多く見られますが、女性や子どもにも発症する可能性があります。「単なるいびき」と軽視されがちですが、心筋梗塞や脳卒中といった重大な合併症のリスクを高める原因にもなります。
睡眠時無呼吸症候群かも?とご不安な方は、尼崎市の兵頭内科眼科・ハートクリニックにご相談ください。当院では簡易検査で診断を行うことができ、重症度に応じてCPAPなどを使った治療も行うことが可能です。
睡眠時無呼吸症候群 中枢性と閉塞性2つの主要タイプ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)には主に2つのタイプがあります。「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」は気道が物理的に閉塞することにより、呼吸が妨げられるタイプで最も一般的です。一方で、「中枢性睡眠時無呼吸(CSA)」は、脳が呼吸を指示しなくなることで呼吸が止まるものです。どちらのタイプであっても、放置することで健康への影響が深刻になる可能性があるため、適切な理解と対応が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)発症メカニズムと原因
睡眠時無呼吸症候群は、主に気道の狭窄や閉塞によって引き起こされます。特に閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の場合、喉の筋肉が過度に弛緩し、気道が塞がれることで呼吸が止まります。このような状態になる主な原因としては、肥満による喉周りの脂肪の増加や、生まれつきの身体的特徴(小さい顎、大きな舌)、さらに鼻炎やアデノイド肥大といった耳鼻科的疾患が挙げられます。
また、アルコールの摂取や睡眠薬の使用、寝る姿勢なども無呼吸のリスクを増加させる要因となることがあります。遺伝的な影響や加齢による筋力低下もこの病気の発症に関与しています。一方で、中枢性睡眠時無呼吸(CSA)は脳の呼吸中枢が指令を出さないために呼吸が止まるもので、心不全や中枢神経系の疾患が原因となることが多いです。
どのような人がなりやすいのか:リスク要因
睡眠時無呼吸症候群は、特定の条件を持つ人で発症リスクが高くなります。特に肥満のある方は、喉周りに脂肪が付きやすいためリスクが高くなります。また、男性は女性と比べて発症率が高い傾向があります。ただし、女性も閉経後にはリスクが急増するとされています。
加えて、首周りが太い、顎が小さい、大きな舌や扁桃腺を持つといった身体的特徴を持つ方も、気道が狭くなることから影響を受けやすくなります。そのほか、慢性的な鼻炎やアレルギーがある人、アルコールの摂取量が多い人、喫煙者、また高齢者もリスクが高いと言われています。これらの特徴を持つ方は特に注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群が日常生活に与える影響
睡眠時無呼吸症候群が原因で睡眠が断続的に中断されると、慢性的な睡眠不足を引き起こします。これにより、朝起きたときにスッキリしない感覚や、日中の眠気を繰り返す原因となります。十分な睡眠が得られない状態が続くと、心身の疲労が回復せず、生活全般の質が低下してしまいます。社会生活を送るうえで必要な集中力や判断力も低下し、日常的な活動にも支障が出ることがあります。
身体的健康への影響:疲れや倦怠感
睡眠時無呼吸症候群は、身体的健康に深刻な影響を及ぼします。この病気により睡眠中に呼吸が繰り返し止まることで、体内の酸素供給が低下し、心臓や脳を含む全身に負担をかけます。具体的な影響としては、高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった重大な疾患のリスクが増加します。また、夜間に深い睡眠が妨げられるため、日中の倦怠感や疲労感が強まり、免疫機能の低下にもつながることがあります。
仕事・生活でのパフォーマンスへの影響:集中力低下
日中の強い眠気や集中力の低下は、仕事や勉強、家事といった日常生活のパフォーマンスに直接影響を及ぼします。特に、注意力や判断力が必要な業務に従事している場合、睡眠時無呼吸症候群による影響は深刻です。また、仕事のミスが増えたり生産性が低下したりするため、職場での評価やキャリアにも悪影響が出る可能性があります。さらに、家庭生活においても活力を失い、積極的な活動が困難になることがあります。
精神的な不調との関係:気分変調
睡眠時無呼吸症候群は日常の睡眠の質を低下させるため、精神的な健康にも悪影響があります。慢性的な睡眠不足や浅い睡眠状態が続くことで、ストレスや鬱状態が引き起こされることがあります。また、集中力や記憶力の低下を招くため、日常生活の中で精神的な疲労感が強まることも特徴です。このような精神的な不調は生活の質を著しく低下させ、他の病気の引き金にもなる恐れがあります。
交通事故や労働災害の可能性
睡眠時無呼吸症候群による日中の強い眠気は、交通事故や作業中の事故リスクを大幅に増加させます。たとえば、自動車運転中に発生した交通事故の原因として無呼吸症候群が関連しているケースが報告されています。特に長時間の運転や単調な作業を行う場合、本人の意思に反して眠りに落ちることがあり、突発的な事故や労働災害の危険性が極めて高まります。そのため、睡眠時無呼吸症候群を早期に診断し、適切な治療を受けることが重要です。
睡眠時無呼吸症候群の診断と治療方法
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が停止することを特徴とする病気です。まずは、セルフチェックで症状の確認を行うことが重要です。
まずはセルフチェックや家族のチェックを
次のような症状が見られる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が考えられます。
代表的な症状として、大きないびきをかく、日中の強い眠気、朝起きたときの頭痛、夜間頻繁にトイレに行くなどが挙げられます。また、「寝ている間に何度も呼吸が止まっている」と家族や周囲から指摘されることも、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重要な兆候です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断基準では、無呼吸低呼吸指数(AHI)が用いられます。これは1時間あたりに発生する無呼吸や低呼吸の回数を表し、AHIが5以上であればSASと診断され、中等度以上の場合は治療が推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の主な検査方法
睡眠時無呼吸症候群の診断には、医療機関による専門的な検査が必要になります。簡易検査としては、自宅で簡単な装置を就寝中に装着いただき、睡眠状態を測定する方法です。それでも診断がつかない場合は、睡眠ポリグラフ検査を行います。これらの検査では、睡眠中の呼吸状態、心拍数、血中酸素濃度、いびきの状態などを測定します。これらの検査結果を基に、SASの有無や重症度が判断されます。
早期に検査を受けることで、合併症のリスクを軽減できるため、症状が疑われる場合は速やかに医療機関へ相談しましょう。
睡眠時無呼吸症候群の治療法:持続陽圧呼吸療法(CPAP)
持続陽圧呼吸療法(CPAP:Continuous Positive Airway Pressure)は、睡眠時無呼吸症候群の治療において最も効果的かつ一般的な方法です。この治療法では、専用の装置を用いて鼻や口に一定の圧力をかけた空気を送り込むことで、気道が閉塞するのを防ぎます。CPAPを使用することで、睡眠中の無呼吸や低呼吸が大幅に減少します。その結果、睡眠の質が改善され、日中の眠気や疲労感が軽減されるだけでなく、心血管系疾患のリスクも低下します。
外科的治療とその他の選択肢
持続陽圧呼吸療法(CPAP)の効果が不十分、あるいは適応が難しい場合、外科的治療も検討されることがあります。代表的な手術には、気道を広げるための扁桃摘出や顎の形状を整える手術などがあります。また、鼻づまりの改善を目的とした鼻腔手術も施されることがあります。
こうした外科的治療が必要な場合は、適切な医療機関をご紹介させて頂きます。
他にも、軽症から中等度の患者にはマウスピース(口腔内装置)の選択肢があります。この装置は、下顎を前方に保持することで気道を拡張し、無呼吸の発生を抑えます。
治療方法は個人の症状や体質によって異なるため、最適なアプローチを選択することが大切ですので、まずは尼崎市の兵頭内科眼科・ハートクリニックにご相談ください。
日常生活でできる改善方法と予防策
生活習慣の見直し(体重管理、禁煙、アルコール制限など)
睡眠時無呼吸症候群の予防や改善には、生活習慣の見直しが重要です。特に体重管理は大きなポイントとなります。余分な体重は喉周りに脂肪を蓄積させ、気道を狭める原因となります。そのため、適切な食事や運動を習慣づけることでリスクを減らせます。
また、喫煙は気道を刺激して炎症を引き起こし、無呼吸を悪化させる可能性があります。禁煙により気道の健康を保つことが可能です。さらに、アルコールは筋肉を弛緩させる作用があり、睡眠中に気道がふさがりやすくなるため、飲酒は控えめにするか就寝前のアルコール摂取を控えることが推奨されます。
睡眠環境の改善
快適な睡眠環境の整備も重要です。睡眠時無呼吸症候群の方にとって、適切な姿勢やベッドの設定が無呼吸を予防する助けとなります。例えば、仰向けで寝ると気道がふさがりやすい方は、横向きで寝るよう心がけるとよいでしょう。また、枕の高さを調整することで、首が無理な角度にならないようにすることも重要です。さらに、寝室を温度・湿度面で快適に保ち、安眠を促進できるような環境を作りましょう。
ストレス管理とメンタルヘルスケア
日常生活においてストレスを溜め込まないことも、睡眠時無呼吸症候群の改善に寄与します。ストレスは睡眠の質を低下させ、無呼吸の症状を悪化させることがあります。そのため、心身をリラックスさせる習慣を取り入れることが大切です。例えば、軽い運動やヨガ、深呼吸法、趣味を通じた気分転換などが効果的です。
筆者情報
- 兵頭内科眼科・ハートクリニック
- 院長:兵頭 永一(ひょうどう えいいち)
- 1998年3月大阪市立大学医学部卒業
資格・専門医資格
- 日本循環器学学会認定 循環器専門医
- 日本内科学会認定 認定内科医・総合内科専門医
- 日本超音波医学会認定 超音波専門医
- 日本脈管学会認定 脈管専門医
- 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施・管理委員会認定 血管内レーザー焼灼術実施医・指導医
- 日本心エコー図学会認定心エコー図専門医
- 身体障害者福祉法指定医(心臓)
- 医学博士